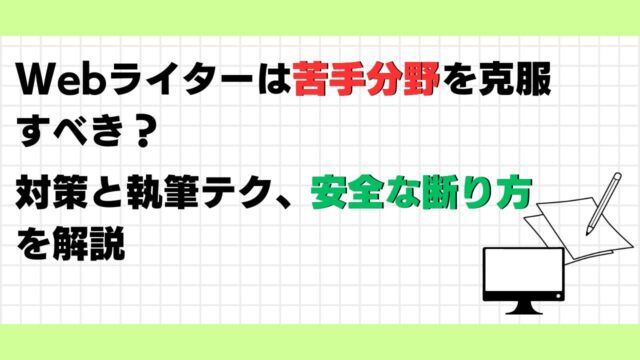
Webライターとして活動する中で、避けては通れないのが“苦手分野”の案件。専門知識が求められるジャンルや、自分の興味がないテーマの記事を書くのは、正直なところ気が重いですよね。
しかし苦手分野を克服できれば、ライターとしての仕事の幅はグンと広がります。収入アップやクライアントの信頼度アップにもつながるかもしれません。とはいえ「どうやって克服すればいいの?」と疑問に思う人も多いはず。
そこで本記事では、苦手分野を克服するための具体的なロードマップや実践的なテクニックまで、余すことなくご紹介します!「苦手だから避ける」のではなく「苦手を得意に変える」ための一歩となる記事です。
スポンサードリンク
目次
これ、書くの辛いかも…Webライターにとっての苦手分野とは何か
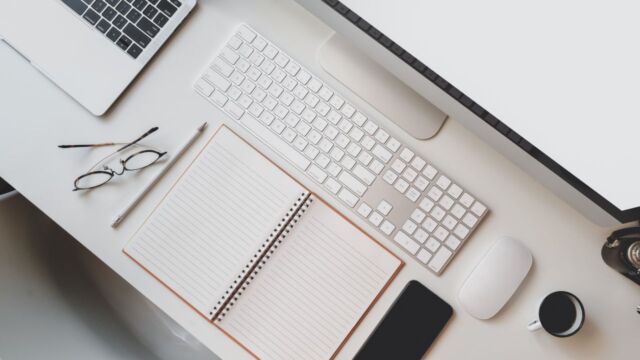
Webライターにとっての苦手分野とは、大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 専門知識のレベルが高い分野:金融、医療、IT、法律 など
- 興味・関心が持てない分野:スポーツに興味がないのにスポーツ記事を書く など
- ターゲット層を理解しにくい分野:男性向けファッション記事を女性ライターが執筆する など
自分が感じている苦手分野の種類がどれに当てはまるのかがわかれば、対策もたてやすくなります。
- 専門知識のレベルが高い分野:知識を得る、学習する
- 興味・関心が持てない分野:その分野の好きなところや惹かれるところを見つける
- ターゲット層を理解しにくい分野:身近にいるターゲットに近い人に聞く
また、基本的にはどの種類であっても「リサーチ」「学習」「経験」の積み重ねが苦手の克服のカギです。
これらを積み重ねていくことで、誰でもある程度は記事の質を担保できます。
苦手分野でも質の高い記事を書くためのWebライター実践テク

「苦手な分野の記事を書くと、なんだか内容が薄っぺらくなってしまう…」
そんな悩みを抱えている人は多いはず。
しかし、いくつかのテクニックを押さえれば、たとえ専門知識がなくても“質の高い記事”を書くことは十分可能です。
ここでは、苦手分野をカバーするための実践的なライティング技術を紹介します。
徹底的なリサーチを行う
苦手分野の執筆の際は、徹底したリサーチで苦手をカバーしましょう。
間違った情報を発信しないためにも、リサーチ力を鍛えることが必須です。
リサーチのポイント
- Google検索では「site:.go.jp」などの検索コマンドを使い、公的機関のデータを優先的に探す
- 信頼できる専門サイトかどうかを確認する
- 参照先の更新日をチェックし、常に最新の情報を活用する
信頼できる専門サイトかどうかの見極めは難しいところですが、企業情報が詳しく載っているか、どんなことを専門にしていて何を提供しているのかなどを確認するのが理想です。
初心者目線で記事を書く
苦手分野の最大の強みは、専門家ではなく初心者目線で書けることです。
自分が初心者であるからこそ、同じ初心者の読者の心理も理解しやすくなります。
苦手分野のリサーチをしたときにわかりにくかったこと、疑問に感じたことをメモしておけば、それがそのまま執筆のヒントになるでしょう。
あとは基本的な記事の書き方と同様に、専門用語はかみ砕く、具体例を用いるといった書き方を組み合わせれば、「初心者が悩みやすい疑問を解消する記事」が作れてしまいます。
苦手分野の執筆においては、初心者と同じ目線に立てることが実は強みになりえるのです。
特にWebライター初心者の方は、読みやすい文章を書くための基本も押さえておき、その分野の初心者に優しい記事を心掛けましょう。
AIを活用してリサーチ・執筆を補助する
「リサーチが大変…」「専門用語が多くて理解できない…」そんなときに役立つのがAIツールです!
例えば金融系の記事を書くときに、「インフレとデフレの違いを初心者向けに説明して」とChatGPTに依頼すれば、噛み砕いた説明を提示してくれます。
AIを活用するときはハルシネーションに注意することと、回答をそのまま使用しないこと。
AIで作らせた記事をそのままコピペしただけでは、価値のある情報とは言えません。
必ずオリジナルの視点を入れたり、自分で咀嚼したりしてから記事に反映してください。
苦手分野×AI活用のコツ
- AIの回答を読んで、自分なりに理解する
- 必ずソースを提示してもらい、ソース先で事実確認する
- 数値などファクトチェックが厳格に求められる情報は目視で確認する
「この用語とこの用語の関係性を教えて」などと指示すれば、その分野を深く理解しやすくなります。
苦手分野でAIを使う注意点は、深い部分ほど自分で正誤が確認するのが難しいことです。
最後には必ずファクトチェックを行い、ハルシネーションなど誤った内容が含まれていないか確認してください。
苦手分野は断っていい?Webライターの立ち回り方

自分のブログであれば初心者目線の記事を書いたり、そもそも書かなければよかったりするのですが、クライアントからの依頼であればテーマが決まっていることが大半なので、そうもいきません。
苦手分野を克服するのもいいですが、時には上手に案件を避けつつ、自分に合った仕事を獲得することも重要です。
「苦手なジャンルの案件がきて困っている…」「断りたいけど、クライアントに悪い印象を与えたくない…」
そう悩んでいるあなたに、案件の取捨選択をするための具体的な方法を紹介します。
リサーチしながら執筆する
Webライターの場合、知らない分野や苦手分野の執筆がくることは珍しくありません。
そのたびに断っていては実績や経歴的にもあまりよくないため、最初のうちは「リサーチしながら執筆する」ことを基本としましょう。
リサーチしても書くのが難しいあまりにも専門性の高い分野もありますが、そういった記事を無理に依頼されることはまずありません。
特にYMYL領域(お金や命など、読者の人生を左右しかねない分野)では、専門性が重視されます。
そのため、そういった分野を「知らなくてもいいから」と強引に依頼してくるクライアントは避けるほか、きっぱり断って問題ありません。
一緒に仕事をしてもほとんど得るものはないでしょう。
例えばYMYL領域といっても「個人でできる節約術」「太りにくい食べ順」などのライトなテーマなら、リサーチしながらでも書けると思います。
苦手分野の執筆依頼がきたら、
「〇〇については詳しくなく、リサーチに時間がかかるため、納期を〇日にしていただけないでしょうか。」
などと一言添えておけば先回りでき、工数を握りやすくなったり、納期を調整しやすかったりするでしょう。
これならクライアントには正直に「あまり得意ではないこと」も伝えられますし、一方で仕事への意欲ややる気も見せられます。
苦手と提案をさりげなく混ぜて、それでも良いと言ってくれた場合に受けるようにしましょう。
丁寧に断る
あまりにも専門性が高すぎる、どうしても苦手分野の執筆は避けたいのであれば、専門外であることを伝えて丁寧にお断りします。
専門性の高すぎる記事を強引に依頼するクライアントは少なく、依頼としても「〇〇の分野って執筆できますか?」とくることが多いはずです。
ただし、知識のあるリーダーが最後に確認するからなどの理由で、確認なく任されることもゼロではありません。
「〇〇という分野は専門外であり、記事の品質を担保できる可能性が低いため、申し訳ありませんが辞退させていただきます。」
ただし、連続で何回も断りすぎたり、苦手や専門外を理由にしすぎたりすると、「この人は調べて書くことができない」「学ぼうとする姿勢がない」とみられる恐れがあります。
断るのは専門性を重視する分野や、そもそも知見がないと書けない分野だけにして、基本的には「リサーチして書く」ようにしたほうがいいでしょう。
苦手の克服も視野に入れる
苦手分野を避け続けると、案件の選択肢が狭まることもあるでしょう。書けるジャンルが多いに越したことはないので、苦手の克服を視野に勉強することも大切です。
克服するかどうかのポイントは以下になります。
- 「好き」「興味」を見出せそうな分野か
- 報酬相場が自分の希望する水準の分野か
- 学びが苦にならない分野か
- 長い目で見て将来的に役立つ分野か
あまりにコスパが悪かったり、相性が悪かったりする分野だと、得意になる前に嫌いになってしまう恐れもあります。
いきなり苦手を克服しようとせず、まずは上記のポイントを照らし合わせて判断するのがおすすめです。
安易に手を出すと時間や体力をムダにする可能性もあるため、「学ぶこと」「学ばないこと」を取捨選択してからにしましょう。
【Webライターの成長に】苦手分野の克服ロードマップ

「苦手な分野の執筆なんて無理!」
実は、多くのライターが同じように感じています。
しかし適切なステップを踏めば、苦手意識を減らし、むしろ得意分野に変えることも可能です。ここでは、具体的なロードマップを紹介します。
苦手な中でも興味が持てそうなジャンルを選ぶ
苦手なジャンルすべてを克服する必要はありません。広く見ると苦手分野でも、範囲を絞ってみると自分の得意分野に近いジャンルや、少しでも興味が持てそうなジャンルに気づきやすくなります。
- 「ITが苦手」でも… → スマホアプリなら毎日触っているから書けるかも?
- 「経済が苦手」でも… → 家計簿をつけたことならある!
こうした視点で考えると、苦手ジャンルでも意外と書けるテーマが見つかります。
苦手分野=全部無理と0か100かの思考になるのではなく、少しでもわかりそうな範囲や好きになれそうな部分を見つけにいくことが大切です。
AIで壁打ち質問をする
実際に記事を書く際にも便利なAIですが、日ごろから苦手分野に関する壁打ち質問をして自分を鍛えるのもおすすめです。
苦手意識の原因の多くは「知識不足」ですが、一から専門書を読むのは時間がかかります。
AIに質問すれば自分から情報を探しにいくのが省けるうえ、嫌がったり面倒くさがったりしないので、気兼ねなく学習が可能です。
執筆時と同様にハルシネーションやソースの確認に気をつけるほか、AIの回答で気になった箇所は自分で調べましょう。
これはAIの活用そのもののコツでもありますが、AIの回答に”疑問を持つ癖”をつけることも非常に大切です。
AIからの情報をすべて鵜呑みにせず、壁打ちはあくまでも学習の補助として活用してください。
小規模案件で実践経験を積む
苦手と感じる理由の一つに、その分野での実践経験がない、あるいは少ないことが考えられます。
小規模な案件や初心者OKの仕事など、できるだけハードルの低い仕事で経験を積むのも有効です。
例えばクラウドソーシングで「初心者OK」の募集を探したり、あえて低単価な仕事で実績を重ねたりする方法もあります。
注意点は、ずっと低単価案件ばかりだとモチベーションが続かないので、いくつか挑戦したら単価をきちんと戻していくこと。
実際に書くことで経験値が蓄積され、自信にもつながっていきます。
オフラインで経験や知識を増やす
苦手と感じている分野が食わず嫌いなだけの可能性もあります。詳しく知ってみれば意外とおもしろかったり、やってみると楽しかったりすることもあるでしょう。
パソコンの前で苦手分野と格闘するだけでなく、実際にその分野に関することに触れてみることをおすすめします。
- ゲーム分野なら → 実際にゲームを遊んでみる
- 金融分野なら → 家計簿をつける、金融ニュースをチェックする癖をつける
- 料理分野なら → 自分で料理を作ってみる
ライターにとって本当に必要なのは、文章力を磨くこと以上に「ライター以外の経験を増やすこと」だと私は思っています。
苦手だと思って敬遠していた分野も、実際に触れてみることで「得意分野」に変わる可能性もあるのです。
まとめ:苦手分野は誰でもある!Webライターとして取捨選択していこう

Webライターにとって苦手分野があることは、必ずしも弱点とは限りません。一から学びを増やせば書ける幅が広がり、新たな案件につながる可能性もあります。
一方で、苦手分野や書きたくない分野を断る勇気も大切です。何のためにこの仕事をしているのかを考えたとき、どうしても苦手分野を書く意義を見出せないのであれば、スパッと断ってしまうのも方法の一つになります。
自分に合った方法でWebライターとしての幅を広げていきましょう!